ASCO2021感想まとめ(2)
こちらから続く

TRUSTY試験 #3507
大腸癌二次治療のFTD/TPI+Bev vs FOLFIRI+Bev
さて次は大腸癌の二次治療の演題を見てみましょう。大腸癌二次治療のFOLFIRIはかれこれ15年くらい今のポジションをキープし続けていますが、FTD/TPIがその座を脅かすのではないかという見方が最近されていました。そこでFOLFIRI+Bevを相手にFTD/TPI+Bevの非劣性を見ようとしたのがTRUSTY試験です。
Dr Yasutoshi Kuboki 🇯🇵 presents OS data which does NOT show noninferiority of TAS102+bev to FOLFIRI + bev in 2nd line metastatic #crcsm in TRUSTY trial #GIonc #ASCO21 pic.twitter.com/WcFqEKr3qY
— Dr Joseph McCollom DO (@realbowtiedoc) June 7, 2021
ぼくは実はFOLFIRIは完敗すると思っていました。FOLFIRIは「時々」非常に良い働きをする患者さんに出会うこともありますが、そういう患者さんはやっぱり少なくて(特にFOLFOXが不応の二次治療では)FOLFIRIは弱いんじゃないかと思っていたので…。しかし開けてみるとこの結果。OSもFOLFIRI+Bevが18ヶ月に対してFTD/TPI+Bevは14ヶ月と、やや残念な感じでした。
それにしても、そもそもFTD/TPI+BevがFTD/TPI単剤と比べてどうなのかという問題は手付かずのように思うので、それも検証しなければならないような気がしていますが。
MyPathway試験 #3004
HER2変異固形がんに対するトラスツズマブ+ペルツズマブ
臓器横断的なHER2陽性/増幅バスケットMyPassway試験のトラスツズマブ+ペルツズマブ単群試験。KRAS変異は抗HER2療法に耐性があることが再確認されたようで、KRAS変異群には治療成績不良です。しかしHER2陽性全固形がんでORR 23.3%、DCR 44.6%、DoR 7.9ヶ月とかなりの好成績です。
🎯Focus on HER2 #NSCLC Interesting findings from a tumor agnostic basket trial targeting HER2 solid tumors (overepression or amplification). Quite similar findings from R2D2 @IFCT trial in the NSCLC cohort (n =27). OR 25%, DoR 8.3m. abstract #3004 #ASCO21 @OncoAlert pic.twitter.com/pXBCOrNMGi
— Julien Mazieres (@JulienMazieres) June 7, 2021
患者背景因子が揃えられていない別集団での治療成績の比較は行儀が悪いので本来は避けるべきですが、数字だけを見ればHERACLES-AのラパカペよりもDCRは低い一方でDoRは長いようです。
これ、ついにHER2陽性大腸癌にトラスツズマブなどが承認される根拠になるんでしょうか?まぁ、HER2陽性大腸癌にはDESTINY-CRC01のT-DXdが控えていてそちらが本命でもあります。
根治切除不能の腎癌を切除するのかどうか問題のFDAプール解析 #4516
🚨 #ASCOtrainee spotlight: @Jaleh_Fallah @US_FDA
— Ana Velázquez Mañana MD MSc (@AnaVManana) June 6, 2021
Survival benefit of nephrectomy prior to immunotherapy-based combinations in patients with metastatic renal cell carcinoma: An FDA pooled analysis.
👉https://t.co/sU1Kc4cNkU#ASCO21 @ASCO #kidneycancer pic.twitter.com/phQnhDJ6Nq
2018年のASCOのプレナリー演題だったCARMENA試験からずっと続く、治癒切除不能な腎癌の原発巣を切除するのかどうか問題。ほとんど有効な薬物療法が無かった一昔前なら腎癌は(卵巣癌などと同じように)治癒切除が不能でもcytoreductionのためにも切除するのが当然でしたが、スニチニブなどのTKI、そして様々なICIが腎癌の薬物療法の治療成績を急速に向上させると、そもそも治癒切除が不能な腎癌に対する初期手術が必要なのかというCQが生まれるようになりました。
2018年発表のCARMENA試験では薬物療法(スニチニブ)のみの群が手術→スニチニブの群に対して非劣性を示したことで、もはやこのタイプの手術は不要ではないかという議論が起こりました(Best of ASCO Japan 2018にも選ばれていました)。しかし、この試験は脱落が多かったりかなり進行例が含まれて手術群に不利だった可能性があることからその後も研究が続けられています。
手術の至適タイミングを探ろうとしたSURTIME試験は症例募集が不調に終わり、有効な解析に至りませんでした。今回のASCO21で発表されたのはプール症例の後方視的解析です。
🚨 #ASCOtrainee spotlight: @Jaleh_Fallah @US_FDA
— Ana Velázquez Mañana MD MSc (@AnaVManana) June 6, 2021
Survival benefit of nephrectomy prior to immunotherapy-based combinations in patients with metastatic renal cell carcinoma: An FDA pooled analysis.
👉https://t.co/sU1Kc4cNkU#ASCO21 @ASCO #kidneycancer pic.twitter.com/phQnhDJ6Nq
これをみると手術群の全生存がやはり優れているようで、TKIをさらに上回るICIが標準治療となってからも手術の有用性が失われていないように見えます。
患者の選び方、試験のデザインの仕方によっても変動しうる結果は解釈に注意
ただし、そもそも長期生存が期待できる患者だからこそ手術をした、あるいは全身状態や併存症の問題で手術を見送らざるを得なかったという背景が多くの症例にあったことを考えると、このデータだけをもってやはり治癒切除が不能な腎癌でも手術をした方が予後が良いとは言えません。
お、これは面白い。
— じなん (@MTCOSB) June 6, 2021
『免疫チェックポイント阻害薬時代において4期腎がんで腎摘は必要ないのでは?』というCQはあったが、後ろ向き解析ではあるもののやはり腎摘を受けた人の方が予後よいとのこと。(当然『長生きが見込まれるから手術する』というバイアスはあるのだが) https://t.co/7KWqB4Kh4x
じゃあRCTならば良いのかというと、たとえRCTを組んだとしてもCARMENA試験がそうであったようにハイリスクな進行がん症例が多くエントリーされれば手術群に割り当てられた症例が過剰なリスクを負う(=薬物療法群に有利なバイアスがかかったセレクションになる)ことになりますし、逆に手術しやすいローリスク症例をエントリーさせればそれは「治験だけでしか成り立たない現実離れした条件が良い症例だけのエビデンス」になってしまいますから、RCTならこの問題を解決できるとは言えないのが難しいところですが。。。
乳癌も大腸癌も予後改善のメリットが乏しく切除を推奨しないっぽい結果になったけど、「切っても切らなくてもOSは大差ない」が示されたのが大事だと思っていて、将来QOLに影響しそうであれば切れるしそうでなければ切らなくて良いという現場の裁量が増えて、個々の状況や希望に応じてやりやすくなった https://t.co/nJY0P1hQVw
— レ点.bot💉💊🧬 (@m0370) June 7, 2021
優劣が付かないということのメリット
優劣がつかないというのは決して悪いことばかりではありません。例えば手術群は明らかに治療成績が劣るとなってガイドラインに明記されてしまうとQOL維持のために手術を選ぶという選択肢を取るハードルがいくらか上がってしまいますし、手術をすべきとなってしまうと望まぬ手術を受けることになる患者が増える懸念もあります。
本来はそうならないようにshared decision makingの考えがあるのですが、そうは言っても日本では依然として主治医の決定権は絶大ですし、また訴訟リスクなどを恐れてガイドラインに杓子定規の治療を行おうとするバイアスがかからないとも言えない。
そういう背景を考えると、手術でも非手術でも予後に大きな差がないと示されたことは患者の希望に応じてどちらの選択肢も選びやすくなった、患者本意の治療を行いやすくなったと考えることもできそうです。こういうデータがないとそのような医療が提供できないのも情けないような気もしますが、まあこれも現実の一側面。
JCOG1407試験 #4017
局所進行膵癌に対する一次治療のmFOLFIRINOX vs GEM/nabPTX
#ASCO21 Poster Discussion Session
— JCOG (@JCOG_official) May 26, 2021
「JCOG1407:局所進行膵癌を対象としたmodified FOLFIRINOX療法とゲムシタビン+ナブパクリタキセル併用療法のランダム化第II相試験」の主たる解析結果が発表されます!
🔎抄録https://t.co/AvHic1yf4w#JCOG #膵癌 #膵がん
試験概要:https://t.co/7BHabEpr8v pic.twitter.com/MPET8nyk97
切除不能進行再発の膵癌ではFOLFIRINOXとGEM/nabPTXのいずれかが一次治療の標準になっていますがその優劣はまだ明確になっていません。JCOG1407試験はこの両者について局所進行膵癌で比較した試験です。
今年の #ASCO21 の注目演題はやはりLAPCを対象にmFOLFIRINOX vs GnPを比較したJCOG1407だろう。https://t.co/6EJzUGFY4J
— уон (@Yoh_tw) May 20, 2021
主要評価項目の1yOSはmFOLFIRINOX 77.4%、GnP 82.5%なんだが2yOS 48.2% vs 39.7%と逆転してる。mOS 2.0y vs 1.8yと同じくらい。JCOG1611はどうなるのかな。
結果的に両者の差はほとんどなく、やはりFOLFIRINOXとGEM/nabPTXは今後も併立の状態が続きそうです。1年生存率はGEM/nabPTX群でわずかに高く、2年生存率は逆にFOLFIRINOX群で高いのは、前者の方が「満遍なくそつなく仕事をする」のに対して後者の方が「選ばれた患者層には高い効果を示す」とみることができるような気もします。
FOLFIRINOXはプラチナレジメンでBRCA変異の影響も大いにあるでしょうから、BRCA変異患者がどの程度含まれていたのかも知りたいところ。
この切り口は確かに盛り上がる。別がん種だがJCOG0603は日本でOX承認直後のため副作用マネジメントに慣れてなくて治療継続に難渋したのではと指摘されてるから、日本でFOLFIRINOX導入初期に始まったJCOG1407も同じようなからくりじゃないかしら。#ASCO21https://t.co/4SVYR7a35q
— уон (@Yoh_tw) May 22, 2021
付いてる海外からのコメントは、違いが無いのは知ってたとか、P2なので多くは言えないとか、非劣性検証デザインじゃないとか、局所進行なのにOS 2年は短いとか、CRTはどうかとか、CA19-9やPSや組織型で層別化しろとか、まあ色々みんな好きなことを言ってる…
— レ点.bot💉💊🧬 (@m0370) June 5, 2021
転移性膵癌ではどうか?
ちなみにこのJCOG1407は局所進行膵癌を対象にしていて、転移性膵癌については現在進行中のJCOG1611試験を待つ必要があります。こちらはFOLFIRINOX群とGEM/nabPTX群に加えて、FOLFIRINOXの5FUをS-1に置き換えたS-IROX群の3群比較試験で、S-IROXがFOLFIRINOXと比べてどうなのかにも注目が集まります。
個人的にはmFOLFIRINOXとGEM/nabPTXは、大腸癌のFOLFOXとFOLFIRI、乳癌のアンスラとタキサンのように「どちらを先にしてもよいが療法を使うことが良い」という結果に収まるのが丸いと思うな(願望)。「標準治療としてはmFOLFIRINOXを優先すべき」みたいな結論が出ちゃったら実臨床はちょっと困りそう
— レ点.bot💉💊🧬 (@m0370) May 22, 2021
KEYNOTE-811試験 #4013
HER2陽性胃癌に対する一次治療の標準化学療法+トラスツズマブ±ペムブロリズマブ
Addition of #Pembrolizumab to #Trastuzumab Plus Chemotherapy Improves Response in Patients With HER2-Positive Advanced Gastric or Gastroesophageal Cancer @YJanjigianMD #ASCO21 https://t.co/Mlh34hC7VF
— Memorial Sloan Kettering Cancer Center (@sloan_kettering) June 5, 2021
HER2陽性胃癌の一次治療ではToGA試験からフッ化ピリミジン+プラチナ+トラスツズマブを使用するのがこの10年間の標準治療でしたが、HER2陰性のほうでCheckMate-649やKEYNOTE-062などの試験が示そうとしたように、当然HER2陽性のほうも既存の標準治療に免疫チェックポイント阻害剤を上乗せすることを目指した試験が組まれています。
KEYNOTE-811試験はFP/CAPOX+トラスツズマブにペムブロリズマブまたはプラセボを上乗せした第3相RCTで、今回はその中間解析結果の結果の発表でした。
中間解析では奏効率が51.9%→74.4%、完全奏効率が3.1%→11%といずれも大きく向上しています。腫瘍が80%以上縮小した割合がペムブロリズマブ群で32%もあり驚異的です(プラセボ群の15%でもかなり優秀でトラスツズマブもパワーを感じますが)。PFSやOSはまだ試験途中で論じるのは難しそう。
米国ではすでにFDA承認済み。日本は?
KEYNOTE-811の登録が終了する前に中間解析でORRだけ発表しちゃって、しかもその抄録が公開された時点でHER2陽性PD-L1>1%胃癌接合部癌にはケモ+トラスツズマブ+ペムブロリズマブが先月既にFDA承認されちゃってるという。ちょっと早まりすぎじゃないのかしら… #ASCO21 https://t.co/eoyRFi7LgC
— レ点.bot💉💊🧬 (@m0370) June 6, 2021
米国ではもうこの抄録が発表された時点でHER2陽性胃癌でのペムブロリズマブがFDA承認されてしまったようです。日本ではOSを見にいく試験の中間解析のORRで承認されるのは難しそうなのでまだしばらく待ちが必要そうですが、これは承認されるのは時間の問題っぽい(あれだけの成績を出していたKEYNOTE-177がOSで有意水準に届かなかったのを聞くと油断はならないですが)。
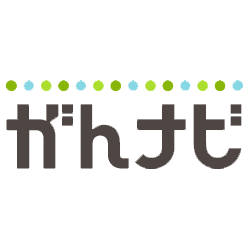
続きはこちら

この記事に対するコメント
このページには、まだコメントはありません。
更新日:2021-06-12 閲覧数:357 views.