ASCO2021感想まとめ(3)
こちらから続く


EA1131試験 #605
術前化学療法でpCRとならなかったbasal-lineトリプルネガティブ乳癌に対する追加化学療法のCape vs プラチナレジメン
Early #BreastCancer Oral Abstract session at #ASCO21: very important data from @eaonc #EA1131 trial (online in #JCO) showing NO superiority or non-inferiority of adjuvant #platinum agent vs. #capecitabine after neoadjuvant #chemotherapy in #TNBC without #pCR@OncoAlert #bcsm pic.twitter.com/U48X38MsxP
— Matteo Lambertini, MD PhD (@matteolambe) June 6, 2021
EA1131試験は、標準的術前化学療法を受けたのち切除を受けたが1cm以上の残存病変がありnon-pCRだったbasal-likeのトリプルネガティブ乳癌に対して、さらにカペシタビンかプラチナ製剤の術後化学療法を上乗せする比較試験です。
術前化学療法でnon-pCRだったトリプルネガティブ乳癌に対して術後にカペシタビンをさらに載せるのはCREATE-x試験で有効性を示されてすでに標準治療となっていますが、術後の追加化学療法の至適レジメンがカペシタビンなのかどうかを検証しようとしたデザインです。
トリプルネガティブ乳癌ですからBRCA変異などとの関連も想起させ、プラチナ製剤による治療がカペシタビンを上回ると予想した人も多かったと思いますが、結果を見てみると、、、
biologyを考えるとプラチナが負けたのは驚きで、逆にワセクロ問題で下火になったカペシタビンの効果が間接的に示されたような気がしないでもないですが乳がんクラスタの方々いかがでしょうか😔 https://t.co/zJpTnOjt8S
— じなん (@MTCOSB) June 7, 2021
これは意外な結果でした。差が無いどころかカペシタビンはプラチナより優れているようです。理由については様々な考察がなされているようです。
basal-likeの中でもgBRCAなどHRDっぽいサブサブタイプの人は術前化学療法の感受性が高いためにnon-pCRとならずに、逆にpCRになってない症例はbasal-likeでもHRRっぽくない人(いわゆるBL2?)がセレクションされてるというようなことも考えられそうです。
《新着図鑑》
— 日本がん対策新聞 (@gantaisaku1105) June 7, 2021
【トリプルネガティブ乳がん:術後治療】術前化学療法後に1cm以上の残存病変が確認されたbasal-likeタイプの人が術後治療を考える場合、「プラチナ製剤」を選択しても「カペシタビン」を選択した場合を上回る3年無浸潤性疾患生存率は期待しにくい。https://t.co/PqVHJVXQCZ
なお、このEA1131試験についてはJ Clin Oncolに早速文献が掲載されています。

FECのFはいらんって言ってみたり5-FU系内服の地固めはアリって言ってみたり、もうわかりませんです(投げやり)
— じなん (@MTCOSB) June 7, 2021
OylmpiA試験 #LBA1
gBRCA変異乳癌に対する術後化学療法としてのオラパリブ vs プラセボ
#ASCO21 plenary begins! OlympiA trial for adjuvant olaparib in high risk HER2-neg early breast cancer improves 3y invasive and distant disease-free survival-- need to keep pushing for BRCA testing in this PARPi world! @ASCO pic.twitter.com/ZPHI9TP75z
— Sarah J. Mah, MD (@SarahJMahMD) June 6, 2021
gBRCA1/2乳癌の術後療法としてのこの辺は乳癌に詳しい先生に解説してもらう方が良さそうなので演題の要点だけ…。
gBRCA乳癌術後オラパリブ1年(OlympiA試験)。3年DFSは局所も遠隔も良好。全生存の解析はHR0.68と良好に見えるけど中間解析の有意水準を0.01に置いたのでp=0.02で未達(昨日のKEYNOTE-361を思い出す)。
— レ点.bot💉💊🧬 (@m0370) June 3, 2021
/NEJM https://t.co/tkkbBOU6TJ
当初はトリプルネガティブ乳癌に限定していましたが途中からはLiminal typeもエントリー可能となったようです。
BRCA変異陽性HER2陰性早期乳癌の術後療法でのオラパリブの優越性がOlympiA試験の中間解析で基準をクリア、早期主要解析へ:日経メディカル https://t.co/2pA3jauOh8 #日経メディカル
— ねこまた見習い (@vc_neco) February 18, 2021
有効中止になるかしら…?
NEJMにも同時掲載され、そのインパクトの大きさが伝わります。
Among patients who had mutations in BRCA1 or BRCA2 and were at high risk for disease progression, those who were assigned to a year of olaparib adjuvant therapy had 3-year invasive disease–free survival of 86%. #ASCO21
— NEJM (@NEJM) June 3, 2021
他にもNEJMに同時掲載された発表も
ついでに、今回のASCO21に合わせてNEJMに掲載されたのは、KRAS G12C変異陽性非小細胞肺癌のソトラシブ(CodeBreaK100)や、進行尿路上皮癌の術後療法としてのニボルマブ(CheckMate-274)などがありました。

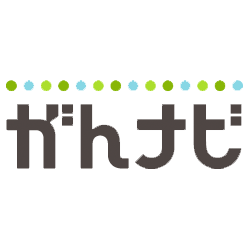

いつもはもう少しNEJMに載ったような気もしたので、もしかして今年はNEJM的には惹かれる演題が少なかったんでしょうか??
他にちょっと興味あるテーマ
MBCに対する化学療法の治療強度を患者さん自身が決めるという発表
MBCに対する化学療法の治療強度を患者さん自身が決めるという発表
— Hawk_Eye (ほーくあい)⛸🐰🐯 (@tkdmHawkeye) June 5, 2021
通常MBCに対する化学療法の強度はpIの結果をもとに決められているが...
86%は有害事象の経験あり
20% ER受診歴あり
83%は減量で症状改善
92%の症例が治療強度を話し合って決めたいと思っている#ASCO2021
周術期化学療法の治療強度は安易に落とさないことが重要ではありますが、一方で根治不能な状況では患者の考え方・価値観に応じてQOLを保った治療を考えることが重要なのは言うまでもありません。
こういう研究はなかなか大々的に取り上げられることがないのが少し残念で、今後こういう観点からの演題も増えてほしいです。ACPとか、老年腫瘍学(Geriatric oncology)にもつながるテーマ。
eNRGy試験 #3003
固形がんの新たな治療標的NRG1 fusion
https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.3003
NRG1が新たなターゲットになりそう。#ASCO21 https://t.co/wxeE1l5Stm pic.twitter.com/jRTPuXJI4s
— Muntari (@SAMuntari) June 6, 2021
eNRGy trialはエナジー試験と読むのでしょうか。
新たな臓器横断的としてNRG1 fusionが注目を集めているようです。ゼノクツズマブ(MCLA-128)の第1/2相試験のウォーターフォールプロットを見ると肺癌が多く「また肺癌かよー」という気がしなくもないですが、膵癌でもかなり見られるマーカーのようで、しかも分子標的治療暗黒大陸だった膵癌でも割と成績が良い。今後に期待です。

U31402-A-U102試験 #9007
EGFR-TKI不応非小細胞肺癌に対する抗HER3-ADC
Patritumab deruxtecan addresses an unmet need in EGFR TKI–resistant, #EGFR-mutated #NSCLC ➡️ https://t.co/oGWttfD6Me #ASCO21 #ASCODailyNews #lcsm pic.twitter.com/fKS9V9OiSP
— ASCO (@ASCO) June 7, 2021
EGFR-TKI抵抗性肺癌への抗HER3抗体を使った新規ADC、パトリツマブデルクステカンの第1相試験。EGFR-TKIの前治療歴があっても(それがオシメルチニブであっても)奏効率39%でDCRも7割前後あるのでかなりの好成績です。HER3(ERBB3)も今後は治療標的になってくるんでしょうか。
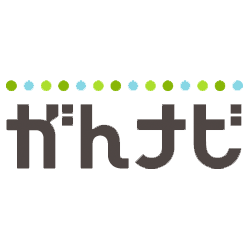
ICIにプロバイオティクス #4513
#ASCO21
— きつね@おんころじぃ (@Kitsunestudy) June 7, 2021
#4513
ホンマかいなww
Nivo+Ipiに整腸剤(CBM-588, 多分日本で言うミヤBM?)を上乗せすると奏効率もPFSも良くなる。たった29例のP1bなので症例数増やしてフォロー期間も延ばさないとなんとも言えないと思うけど。
ニボルマブ+イピリムマブに整腸剤を併用するとORRもPFSも改善するという話。腸内細菌叢とICIの奏効の関係については多種多様な報告が上がっており、細菌叢のdiversityが関係していると言ったり抗菌薬投与は有効性を損ねたりするという話も耳にしますが、今回の研究は29例だけの第1b相のようなので今後の前向き検証的試験が必要ですね。
そもそも経口整腸剤がどの程度腸内に生着しているのか自体がかなり怪しいと思っているので(腸内細菌叢を外部から人為的に変化させるのはそう簡単ではなさそう)、どちらかと言うと経口プロバイオティクスがICIの有効性にそこまでの影響を与えることについてはやや懐疑的に見ています。あるいは、むしろdiversityを低下させてかえって逆効果な可能性もあったりして…。続報待ち。
ASCOとTwitter #11039
Poster by Drs. Gil Morgan @weoncologists et al shows sig #OncTwitter growth over last 5y of @ASCO Annual Mtgs & esp #ASCO20. Nice to see we're finding ways to connect & disseminate #science & #MedEd despite #COVID19. Curious to see how #ASCO21 compares: https://t.co/GFrA8zCyRW. pic.twitter.com/BSRR23O881
— Tatiana Prowell, MD (@tmprowell) June 4, 2021
以前からも海外の学会に比べて日本は(日本循環器学会以外は)うまくインターネット、特にSNSを使えていないと思っていましたが、ASCOはうまくSNSとの融和を進めて行っているように思います。
日本ではまだweb開催が珍しかった頃の2020年6月から完全web開催で実施していますが、Twitter上でのASCOの存在感、あるいはASCOでの Twitterの存在感はどんどん増しているようです。
まとめ
今年は2020年に比べるとなんとなく予想された結果の演題が多くて、開けてビックリということは少なかったように思います。それでもKEYNOTE-811やEA1131など結果の解釈が悩ましいものもあり、また臨床試験の結果がOSの有意差だけでは確定できない新時代になってこの結果が承認許認可当局にどのように判断されるのか気になるものも沢山ありました。
ASCO21のうち注目の演題、またガイドラインを書き換えたりして日本の臨床に影響を与えそうな演題については、業界を代表するエキスパートの解釈を踏まえて解説講演をしてもらえるBest of ASCO Japanが来月に開催されます。
どの演題が採択されるのかは未定ですが昨年は新型コロナウイルス感染症のドタバタで1日に短縮されていたのが今年は2日間に復活しており、今から楽しみです。
この記事に対するコメント
このページには、まだコメントはありません。
更新日:2021-06-12 閲覧数:1983 views.
