学会がSNSを広報に利用してゆくということ
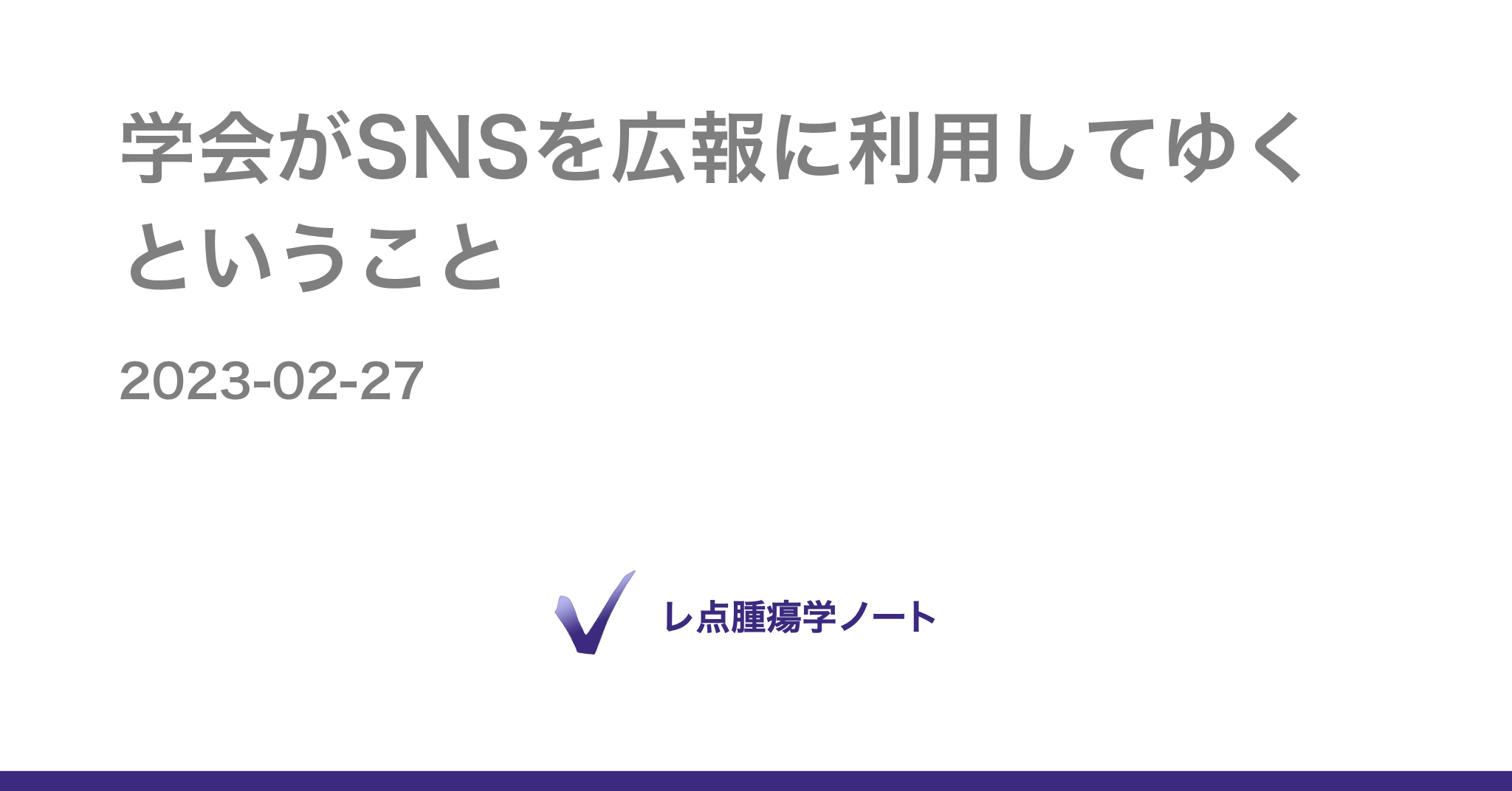
学会の広報活動で活用が進むSNSの位置づけ
近年、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サイト)は、学会の広報活動において欠かせない存在となり、その普及が進んでいます。SNSは、学会や学会の活動をはじめ、広く大学に関する情報を発信することができます。しかし、学会や医療者は必ずしも上手にSNSを使いこなせているわけではありません。ヤンデル先生は、この学会や医療者のSNSの使い方について、どのように考えてゆくべきかということを熱心に啓発されています。

SNSを運用すること自体が広報ではない
ここで重要なのは、SNSを適切に活用すること自体が広報ではない、ということです。
SNSは広報に向いているツールですが、SNSをやること自体が広報になるわけではありません。SNSは、Webサイトや講演資料・書籍などの一次情報がストックされたコンテンツを拡散するためのツールにすぎません。SNSそのものがコンテンツになるわけではないため、素材(コンテンツ)を充実させることがSNS活動の土台になるわけです。
コンテンツを充実させることの重要性はあまり認識されていない
しかし、学会・学者や医療者が一般的な視聴者に訴求するコンテンツを作るための素材の重要性は、実際にはあまり認識されていないようです。WebサイトやSNSを作ること自体が目的になってしまい、コンテンツの重要性が見落とされがちです。
SNSの強みを活かすためには広報委員会だけでなく学会の総合力が必要
SNSの活動に継続性を持たせるためには、SNSを運営する広報委員会が単独でがんばるのではなく、学会企画部会や教育セミナーなど学会の各部署との連携が必要です。学会全体で、SNSを用いた広報に対する理解を深めてゆく必要があります。
これらの内容は、ヤンデル先生がこれまでもTwitterスペースなどで繰り返して発言されてきたことですが、なかなか学会の上層部(に限りませんがSNS広報に関する理解が深くない方)にはわかってもらえない状況が続いています。SNSを上手に扱える組織とそうでない組織の差は広がってゆくばかりになりそうです。
この記事に対するコメント
このページには、まだコメントはありません。
更新日:2023-02-27 閲覧数:266 views.